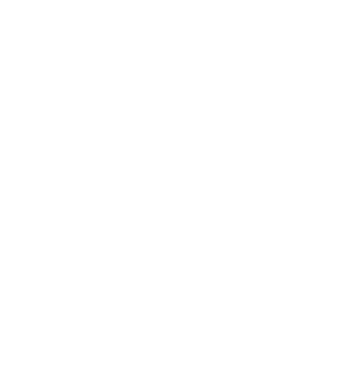新学期を乗りきろう!!
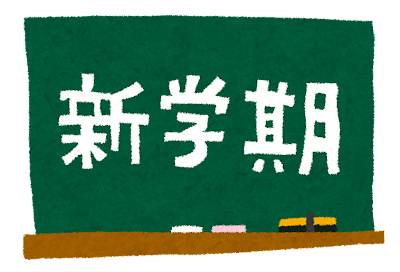
4月に入ると新しく学校に通い始めたり、学年が変わることで以前の環境と比べてルールが変わったり学習のレベルが高くなる等、より忙しくなったと感じる方も多いかと思います。
最近では、「小1プロブレム」「中1ギャップ」「高1クライシス」などとも言われており以前の生活とのギャップから、ストレスを感じやすい季節になっております。
このブログでは、新学期に感じるギャップとその対応や発散方法をお伝えしたいと思います。
新学期に感じやすいギャップ

春休みは短いお休みになるため、生活リズムが崩れてしまったときに修正がしずらい特徴があります。
休みの間にスマホゲームなどで昼夜逆転の生活をしてしまうことで、日中の生活に上手く切り替えられず新しい環境に適応しずらくなってしまうことがあります。
長期休みの前は日中の過ごし方を親子で話し、ゲームやお出掛けなど「好きなことをする時間」やお手伝いや宿題や寝る時間などの「やらなければならないことをする時間」をバランスよく組めると良いでしょう。
ストレスサインに気を付けよう
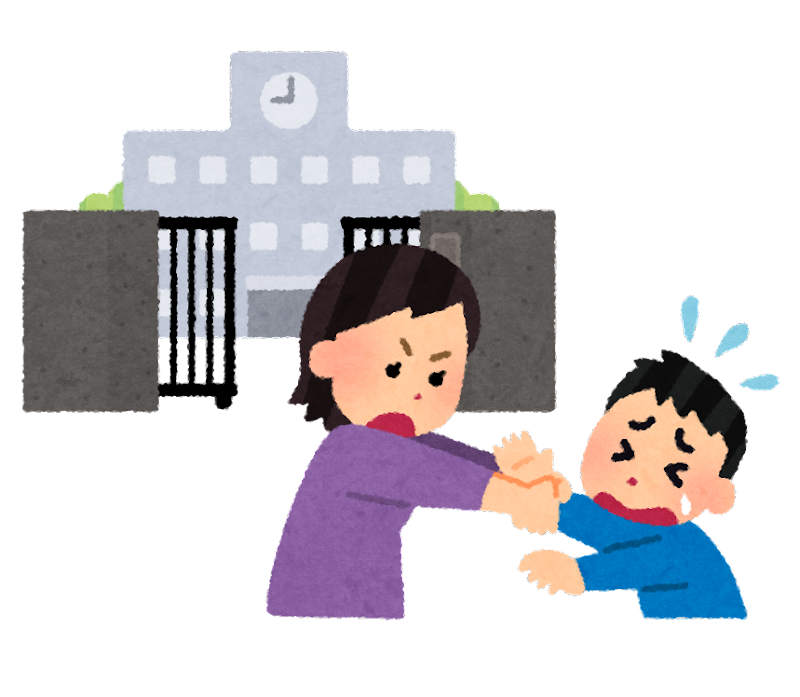
小学生のお子様にとっては、遊びの中で学んできたことが机上での学びに変わったり、規律を重視した学習を受けることが増えてくるため戸惑ってしまうことがあります。
中高生になると生活する集団が大きくなることで、人間関係が複雑になったり定期試験の結果や成績が進路に反映されることが増えることで学校に行くことが嫌になってしまったり、ストレスに感じるお子様がいます。
このような問題は家庭では対応や察知をしずらいため、お子様のストレスサインに気づくことが大切になります。
お子様に表れやすいストレスサインとして学校に行く時間にお腹の痛み、食欲がなかったり、感情の起伏が激しくなったり、口数が少なくなるなどがあります。
また、ストレスサインはひとによって現れる内容がかわるので、あらかじめ家族内で把握しておくこともストレスサインに気が付くキッカケになります。
ストレスを発散させよう
1.定期に好きなことに没頭する時間をつくる。

学校や習い事など以外に興味があることがあったら家族で取り組んで遊んでみましょう。家族が一緒に同じもので遊ぶことで、ちょうどいい切り上げのタイミングを伝えることができます。
2.なにもせずに家でゆっくり過ごす日をつくる。
新生活がはじまると慣れない環境のため、普段は普通に通えている習い事などが負担になってしまうことがあるため、優先順位を変えて習い事は新生活に慣れてから再開するのがおすすめです。
3.ゆっくり話したり、スキンシップをとる。
学校から帰ってきて元気がない時は親子でなにがあったかゆっくり話すことも大切です。大人からみたら簡単な悩みかもしれませんが、子供にとってはとても大きな悩みの場合もあるので、否定せずにお子様の話を聞いてあげることでお子さんも安心感を持つことができます。
まとめ
今回は新学期に感じるストレスについて書きました。
お子様の異変を感じた時にはご家庭が一番身近な存在になりますが、お父様やお母様も一人で抱え込まずに判断が難しい場合はスクールカウンセラーや教育相談センターや精神科・心療内科などに相談に行くことも大切です。
新学期をたのしく乗り越えられるように家族で対策をしてみてはいがかでしょうか?