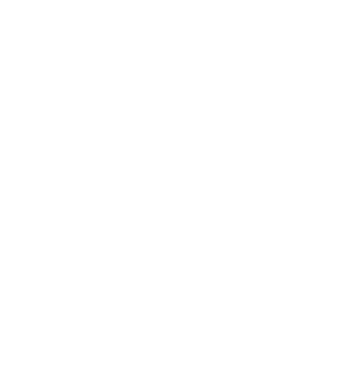「学習支援」について考える

「学習支援」って?
学習支援というと、LD(学習障害)を抱えた子どもへの支援をイメージしやすいですが、自閉症症状を抱えたお子さんも学習につまずきやすく、寄り添って支援をしていく必要があります。
LD(学習障害)は、読み書き障害・書字障害・算数障害と文字や記号を対象に苦手なお子さんに診断が出ますが、読む・書く・話す・聞く・計算・推論の分野で継続的に困難な状態であれば、どんどん支援を入れていく必要があるでしょう。完全に勉強に遅れが出てから支援に入るのではなく、その前の段階で支援に入るのがベターです。
学習支援の意義は、学習の遅れをカバーし自己肯定感を回復させる、将来の可能性を明るくする事ですが、二次障害としての非行や引きこもり・不登校の予防をする事にもあるのです。

言語の大切さ
「お友だちの事を考えられるようになって欲しいです。」
こちらの言葉は、優先順位は違えどほぼ100%の親が子どもに望むものです。
相手の視点に立って考える力が低い子どもは、相手の事を考える事が苦手です。9歳程度の言語発達までしっかり伸ばすことによって、相手の立場で考えて、言葉を使って気持ちを推論する事ができるようになります。
例えば、A君がなぜ泣いているのか分からない/喜んでいるのか分からない・・・が言葉を使って推論することによって、「さっきB君に悪口言われたから泣いているんだろう」「先生に褒められたから喜んでいるんだろう」と推論する事が出来るようになります。
では、言葉や語彙はどのようにして増えていくのでしょうか。本を読んで取得するのでしょうか?テレビ等の映像を見て覚えるのでしょうか?
本やテレビ等での言葉の習得は後から追加される部分であり、言葉や語彙が増える土台は、体験や経験です。体験や経験をしている時に言葉をかける事によって、言葉を覚えていくのです。
行楽や公園、生活や学校、放デイでの経験やコミュニケーションにより語彙力を伸ばしていきましょう。

人の気持ち・感情の言語
国語を学ぶ時に、人の気持ち・感情の言葉を学びます。
- 心情描写(低学年)→「A君は嬉しくなりました。」
- 行動描写(低学年)→「B君は笑顔になりました。」
- 色彩描写(中高学年)→「全ての景色がモノクロ写真のように見えました。」(ショックを受けた様子)
- 情景描写(中高学年)→「空には虹がかかっていました。」(問題が解決して明るくなった気持)
心情描写や行動描写は直接気持ちが書かれているので分かりやすいです。
中高学年から色彩描写や情景描写を学びます。色や情景で気持ちを表現する言語ですが、これを直接正面から捉える子・感情表現に乏しい子には、難しいです。
まずはプラスの気持ちなのか、マイナスの気持ちなのかだけでも教えてあげて、事前にどういうものか見通しを伝えておいた方が分かりやすく混乱におちいりにくいでしょう。
こだわり、学習遅滞、不登校、多動、注意散漫、音に敏感など、お子さまの発達・成長・学力でご不安なことがありましたら、ご相談ください。
- 準備や時間管理が苦手
- 空気がよめない
- こだわりがあり学習にも偏りが多い
- 意外なことで突然癇癪を起す
- 不登校で勉強が遅れている
- 算数や国語の問題内容をイメージするのが苦手
放課後等デイサービス オレンジスクール 藤沢第2教室
(ST)