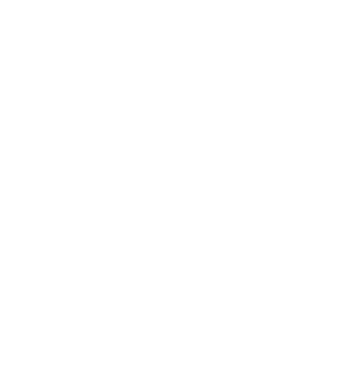音読のしかた
こんにちは、オレンジスクール鶴見教室です。
今年も残すところあと2か月を切りました。
オレンジスクール鶴教室では、クリスマスプレゼントの話題や、「来年から〇年生になるんだー」といったお話が聞こえてくるようになっています。
■さて今回は、音読についてです。
特に小学校低学年では音読は宿題にもなるなど、非常に重要視されている部分ですね。

音読は、文字を音にすることで、人の脳内で文字と音を紐づけていく練習になります。
実は人が文字を読む時、書くときには無意識下の脳内で、一度文字を音にし、文字と照らし合わせる作業が繰り返されています。
よくある相談
面談でも子さまの学習の特徴として音読についてお話いただくことがあります。
中でも最近よく挙がるのが
「うちの子は文章を丸暗記していて、音読では読んでいる振りをするんです。」
といったお話です。
暗記の中身

お子さまによっては繰り返すことで文章を暗記してしまった結果、作業的に読んでいるという可能性もあります。
その場合、内容の確認などをしてみましょう。
「誰がなんて言った?」「誰が出てくる?」といったように、最初は具体的に答えられる形で確認しましょう。
■文字と音がつながっていない場合
文字と音の繋がりが弱いお子さまは、1字ずつ読むことが非常に苦手なので、「ここから読んでみて?」と促すと、一気にスピードが落ちます。
そうしたお子さまはひらがなやカタカナの読み方を復習していきます。
■単語ごとに分けられない場合
どこで切ったらいいのか分からないことで、読みづらさを感じているお子さまには、間に斜線をいれ、単語ずつのまとまりを示します。
文字をあえて追わないのか、追えないのかの確認をしてみましょう。
練習方法

練習方法として、
- 出来れば文章全体の前に、1文字ずつを指さしながら、大人も一緒に読んであげる。
- 日頃から、文字を読む(単語などでも)ことを繰り返して、文字と音を一致させる練習をしていく。
- 単語ごとに斜線で区切って、読む練習をする。
- 暗記だけで音読する子は、新しい単元に入った時に一緒に概要を確認しながら進めると記憶しやすい。
- 覚えた後は呪文のようになってしまうので、合間合間で内容を確認してあげると、概要も含めて理解しやすい。
といった方法があります。
オレンジスクール鶴見教室では
オレンジスクール鶴見教室では、文章問題を行う際に文章があまり理解出来ていないお子さまには、先ずは音読することを勧めています。
特に視力が低いお子さまなどは耳からの情報に優位性を持っていることがあります。
テレビのCMやお笑い芸人のフレーズや、町で流れていた音に反応してよく真似する傾向にあるお子さまは聴覚からの優位性が高いかもしれません。
音にすることでお子さまにも聴覚からの情報として入りやすくなります。
脳内での整理が難しいお子さまも、口頭で職員が質問すると答えられるような場合もあり、学習習慣の構築の上では、必ずしもプリントを黙読し取り組む必要はないとしています。
最後に
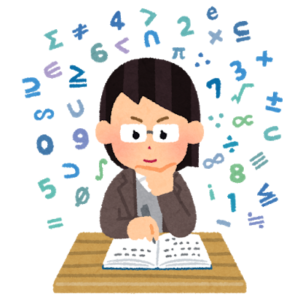
文字を音にする練習は書くときにも使うスキルです。
低学年では連絡帳を書くときにも必要あり、学年が上がると記述することも多くなっていきます。
自分の思いを文字にする作文などでも音にする→文字にするが必要です。
お子さまの特性に合わせて音読の時間を有効に活用できる時間を探していければと思います。