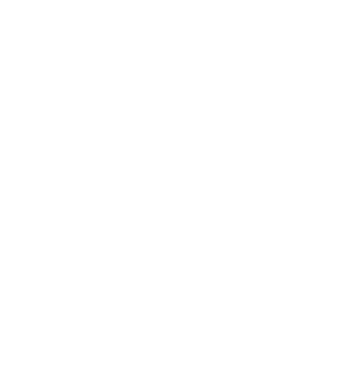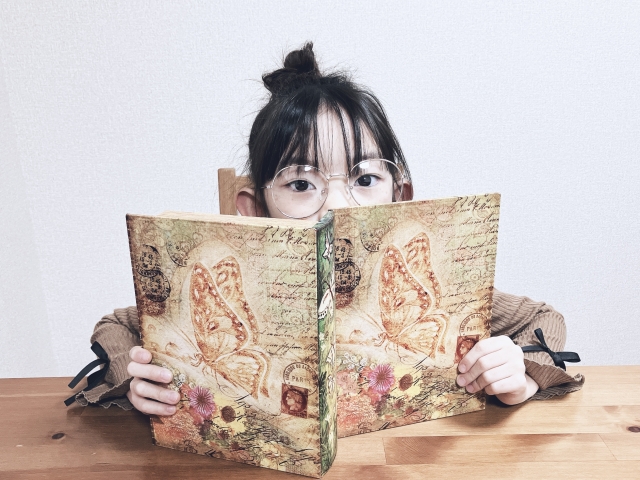
文字を読む力と読み取る力
こんにちは!放課後等デイサービス オレンジスクールあざみ野教室です。
あざみ野教室では、5月に『読書会』と称して、教科書にも出てくるお話をマル読みでつないで読む時間を設けました。
今回は、『読む力』についての取り組みを紹介していきたいと思います。
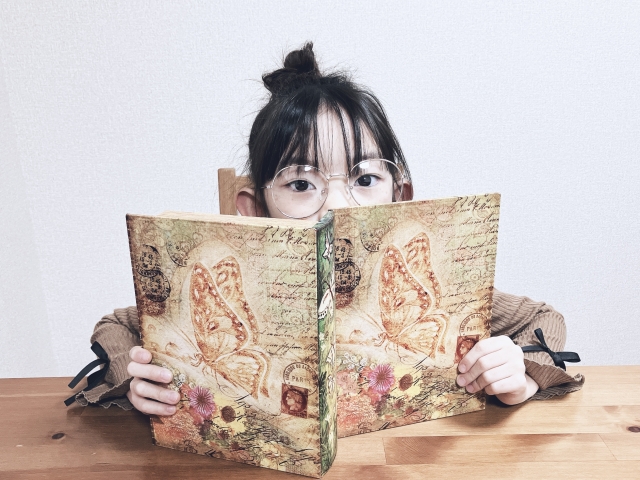
音読で読む力アップ
音読をすることは、読む力をつけるためのとてもいい練習です。
しかし音読をする際、『文字は知っているはずなのに上手にスラスラと読めない』『逐次読みになってしまう』というお子さまも多いと思います。そんな時には、言葉の切れ目がどこにあるかを意識するために、言葉を単語ごとのまとまりで区切る練習をします。ぱっと見て区切る部分がわかるようになると、読みやすさも上がっていきます。
短い文章から練習を繰り返し、長い文章も滑らかに読めるようになると、内容の理解もスムーズになりますね。
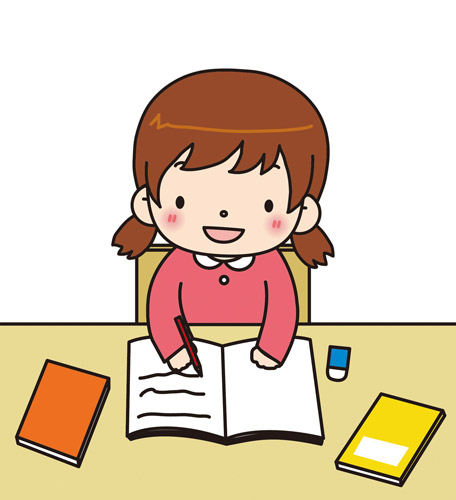
内容の適切な理解に向けて
文章に合う『助詞』や、『動詞の形』を選んだり、考えたりすることを通して、文章の違いに気づけるように練習をすることもあります。例えば、『Aさんが教える』『Aさんに教える』という言葉を見ると、『教える』という動作をする人はそれぞれ異なっていますね。イラストを見て合うものを選ぶワーク、前後の文章を見て考えるワークなどを通して、適切な内容理解に繋がるよう支援をしていきます。難しい時には、職員と相談しながら、場面のイメージを膨らませながら考えていきます。
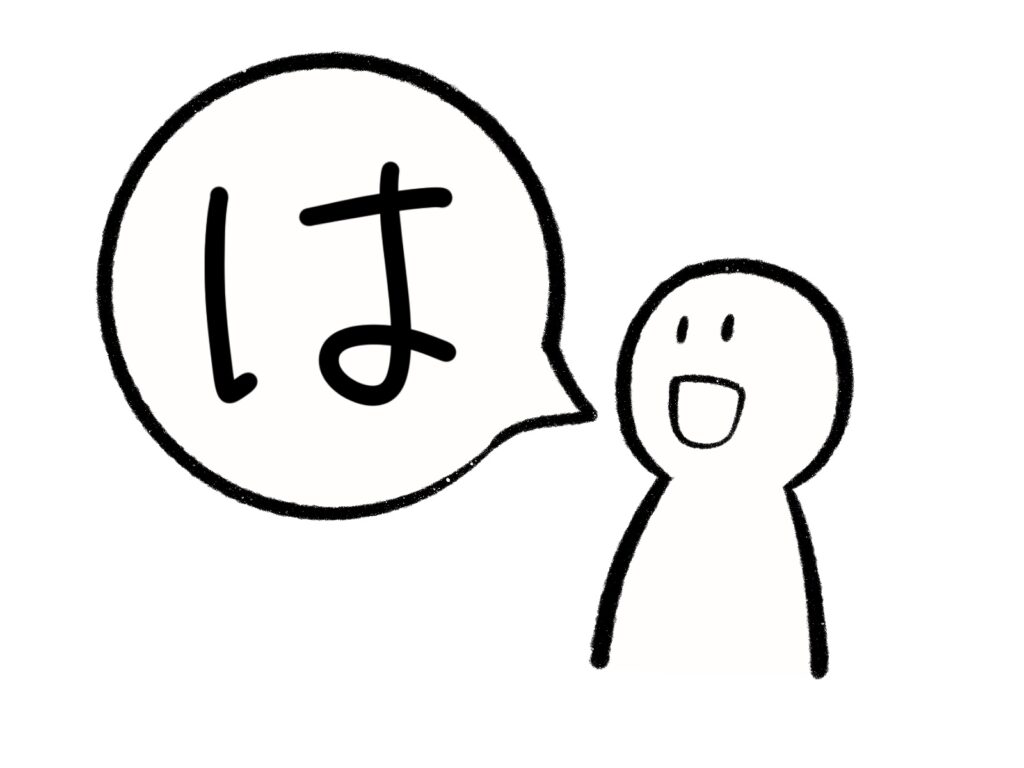
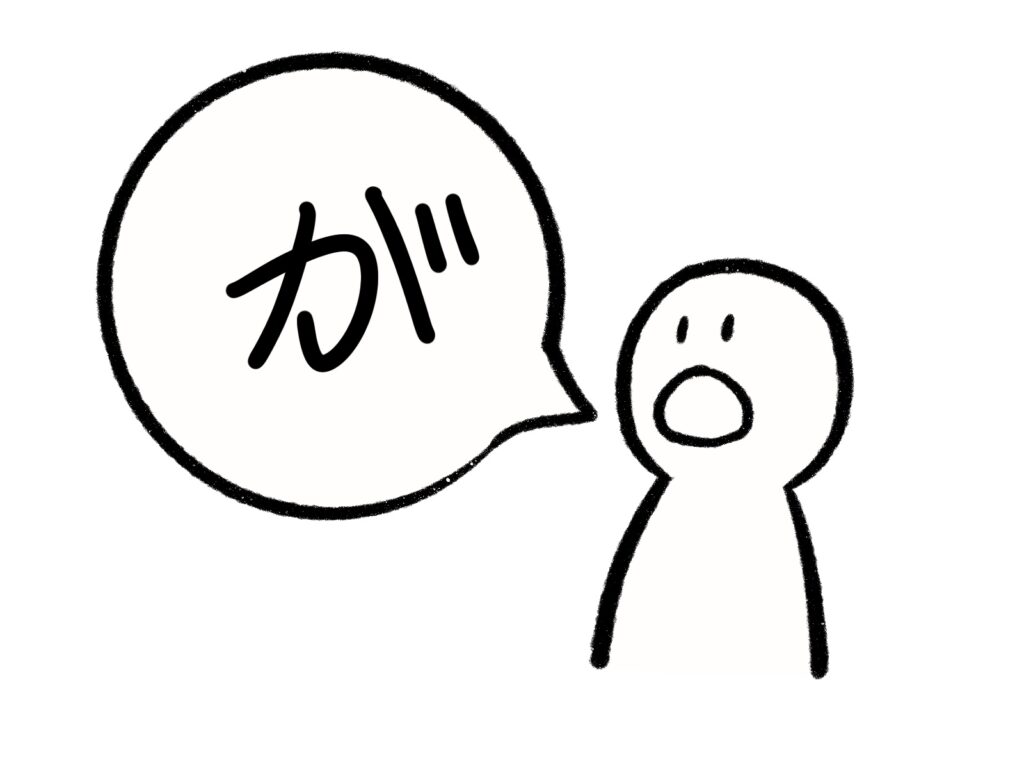
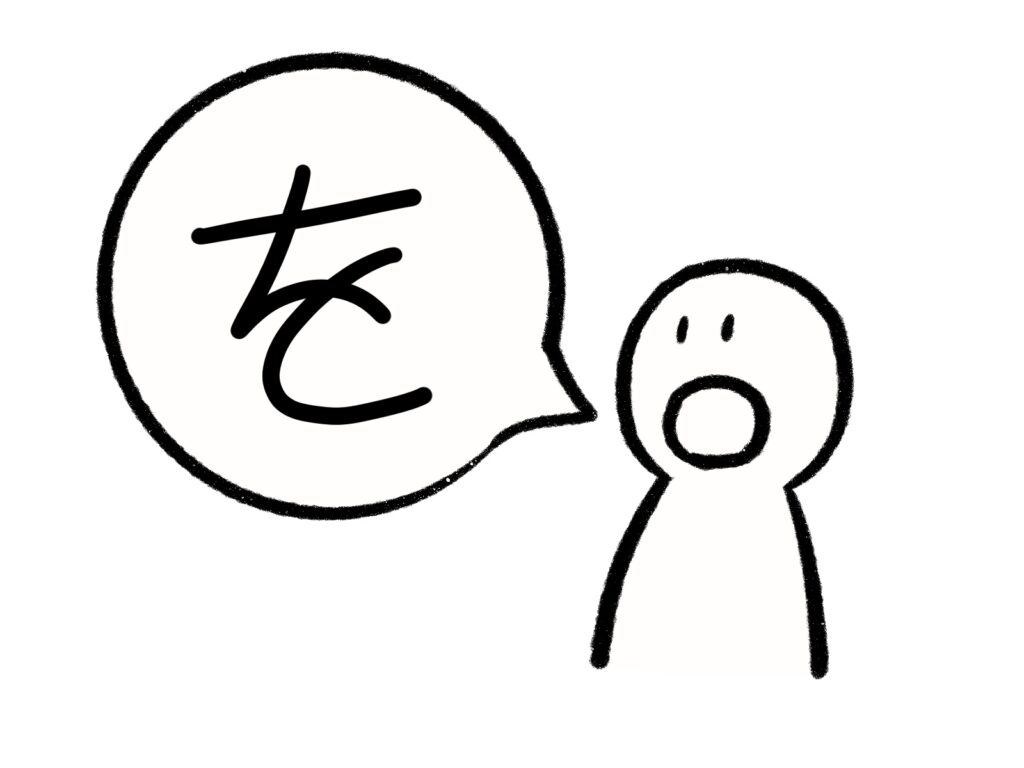
読む時の負担も少なく
目を動かす力の不十分さが理由となり読みづらさを感じているお子さまの場合には、ビジョントレーニングをすることで読むのが上手になっていくこともあります。頭は動かさず、目だけを動かす練習を通して、読んでいる部分を目で追う力の向上を目指していきます。教室でも、プリントを使ったビジョントレーニングを行うこともあります。
先ほどお伝えした読書会などでも、文章を読む時に目で1列を追いかけて読むことが難しいと感じるお子さまは、『リーディングトラッカー』を使うことで読みやすくなる場合があります。読む部分の隣の文字は隠れて見えなくなるため、目の負担が軽減されて文字を追いかけやすくなります。文字を読む際の負担が減ることで、ぐっと内容の理解がしやすくなることもあります。
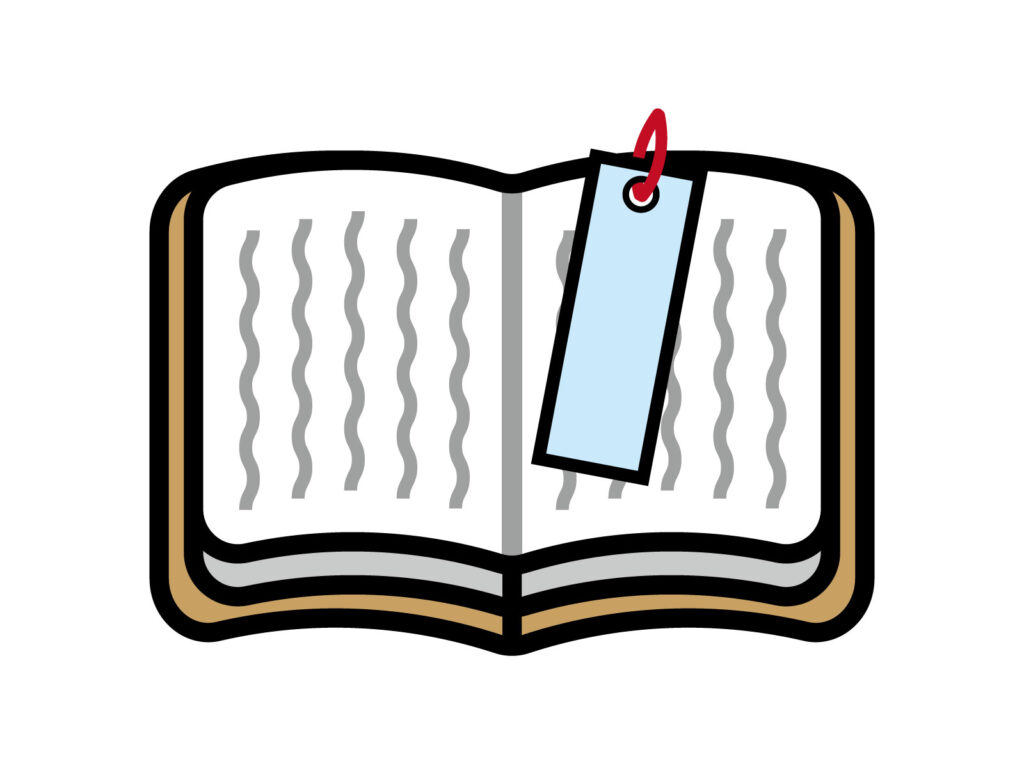
心理・情景の描写の読み取り
内容が複雑になってくると、躓くポイントのひとつとして情景描写や心理描写の読み取りがあげられるかと思います。登場人物の気持ち、場面の雰囲気などを読み取る問題を考える時には、場面を他の言葉で言い換えたり、描写をしたりすると答えがわかることもあります。イメージを膨らませていくことで、理解も深まっていきますね。
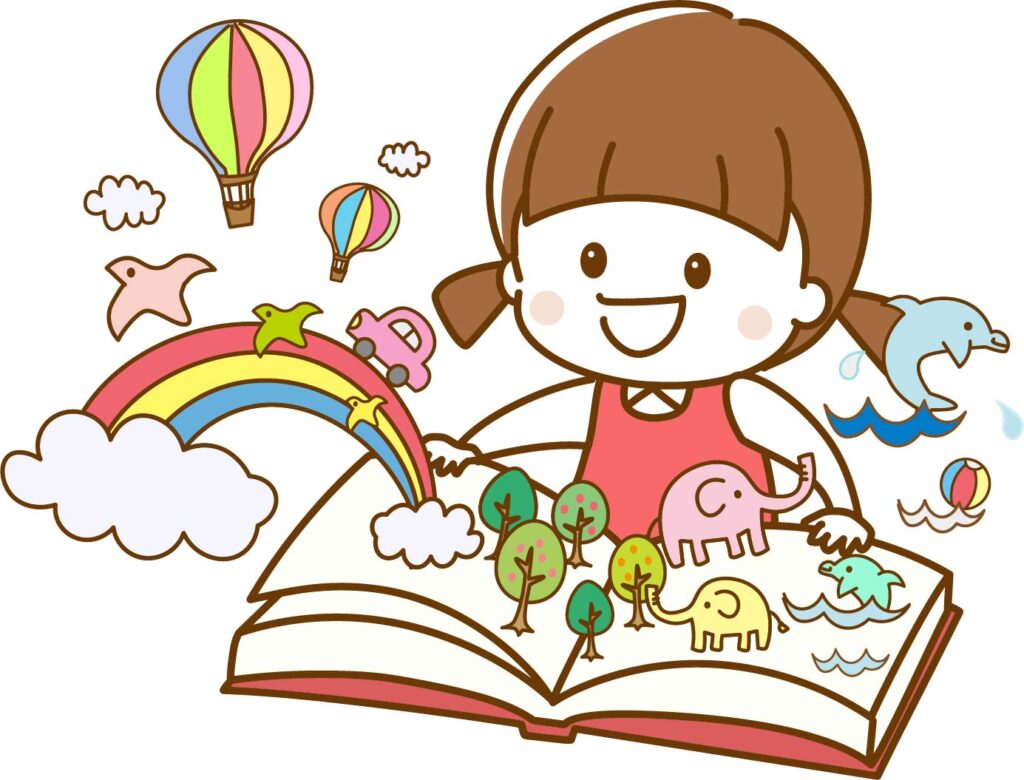
読解問題に苦手意識があり、宿題などで出てきた際に『なかなか手につかない』、『モチベーションが上がらない…』というお子さまもいるかと思います。ご家庭などで一緒に学習をしている時には、問題文の半分はお子さま自身に読んでもらい、残りの半分は大人が音読し、設問に答えてもらう、句点ごとに交互に読んでみる、といったようにすると、読むことの負担を少し減らしながら、『できた!』『解けた』という感覚を持って続けていくことが出来るようになるかもしれませんね。

**********
こだわり、学習遅滞、不登校、多動、注意散漫、音に敏感など、お子さまの発達・成長・学力でご不安なことがありましたら、ご相談ください。
- じっとしているのが苦手
- 準備や時間管理が苦手
- 空気がよめない
- 周囲が気になり集中できない
- こだわりがあり学習にも偏りが多い
放課後等デイサービス オレンジスクールあざみ野教室
【TEL】045-532-3738
【MAIL】azamino@orangeschool.jp
************