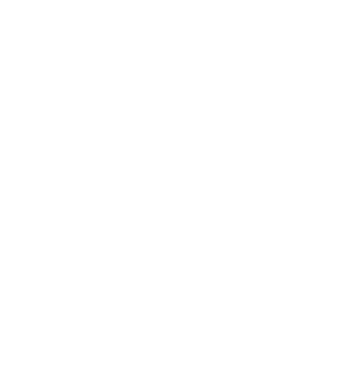【もうイライラしない!】オレンジスクールつくば教室流、発達特性別「学習の集中力」を高める4つのコツ
こんにちは。
オレンジスクールつくば教室です。
今年度も折り返しになりました。授業では応用やまとめがはじまり、基礎の定着が不安定なお子様にとっては辛い場面も増えてきているかと思います。
お子様の中には授業を聞いてもついていけないことで、落ち着きがなくなったり、授業に参加したがらなくなったりすることがあります。
今回は『集中を促す学習方法3選』として、【もうイライラしない!】オレンジスクールつくば教室が教える、発達特性別「学習の集中力」を高める4つのコツをお伝えしていきます。
「授業中に集中できていない」や「宿題がはかどらない」といったお悩みのお役に立てたら幸いです。
【ソワソワ・モジモジ対策】集中力を高めるための「あえて刺激を入れる」
実は「刺激不足」が原因だった?多動・衝動性が高い子の集中力の謎

「刺激は学習の妨げになる」と思われがちですが、衝動性や多動性の特性を持つお子さんの場合、実は「刺激不足」が集中を妨げている可能性があります。
ソワソワ、モジモジといった行動は、脳が刺激を求めているサインです。
この欲求が満たされないと、お子さんは目の前の課題よりも体の動きに気を取られてしまいます。
そこで私たちは、意図的に外部から適度な刺激を入れ、その欲求を穏やかに満たすという逆転のアプローチを採用しています。
背中トントンから立位学習まで!集中力をチャージする3つの外部刺激
ここでは家庭ですぐに試せる、集中力をチャージするための具体的な外部刺激をご紹介します。
- 聴覚:
極めて薄く音楽をかける。 - 触覚:
1.背中を優しくトントンする補助。
2.スクイーズやねり消しを握りながら解いてみる。 - 固有受容覚:
立って解いてみる(立位学習)
これらは、宿題中におしゃべりしてしまう、気が散ってしまうといったお子さんにも非常に有効なのでお試しください。
【事例】「歌わないと解けない子」が落ち着いた「背中トントン」
以前、「問題を解く際に大声で歌わないと集中できない」というお子さんがいました。
この「歌う」という行為が、その子にとって脳を活性化させる刺激でした。
しかしながら教室の環境を考慮すると、どうしても別の方法で欲求を満たす必要がありました。よって教室では以下の支援を行いました。
- 職員が隣に座り、歌うことの代わりとして背中をトントンと一定のリズムで叩く方法を導入。
- 継続すると、職員が手を置いているだけでも落ち着いて学習できるようになりました。
この事例は、外部刺激を上手に活用することで、お子さんの自己制御能力を段階的に伸ばせた事例でした。
お子さんの「ソワソワ」は「集中したい」のサインかもしれません。
【一人でできるを育てる】「集中する」感覚を体験させる魔法の離席術
なぜ「集中しなさい」は伝わらない?
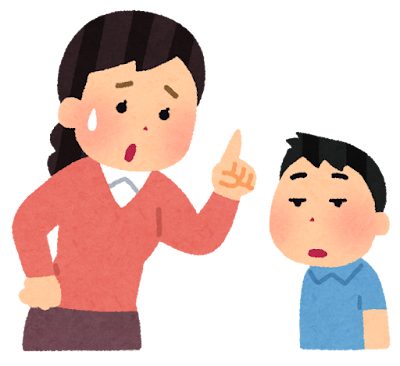
大人が「集中しなさい」と声をかけても、お子さんがその通りにならないことはよくあります。
これは、お子さんにとって「『集中する』って何をすることなのか」という言葉と行動が繋がっていかない曖昧さが原因かもしれません。
教室では、言葉の指示だけで行動を促すのではなく、実際に「集中する」感覚を体験してもらうことで、『集中』という行為への理解を深めることが大切だと考えます。「できた!」という成功体験こそが、次の意欲につながる土台となるからです。
保護者のための「短時間離席」実践マニュアル
お子さんに集中する感覚を体験させるための具体的な方法が、「短時間、意図的に離れてみる」ことです。
宿題や学習の際、「すぐ戻って来るから、1問だけ解いておいてくれる?」「ちょっとお水持ってくるね」といった、大人側が頼む形で声をかけます。
この実践には、成功を確実にするための2つの重要なポイントがあります。
1. 見通しと安心を確保する時間設定
離れる時間は、お子さんが不安を感じず、「すぐ戻って来る」と見通しを持ち、安心できるくらいの短い時間に設定します。
離席が長すぎるとお子様の集中力が切れるため、「1問自分でできたね!」と必ず褒めて終えられる範囲にとどめてください。
慣れてきたら、「水を飲んでくる」→「郵便受けを見てくる」→「洗濯物を取り込んでくる」のように、離席する時間を段階的に長くしていきましょう。
2. モチベーションに一味加える「お願い」
「~しなさい」ではなく、「~してみてくれる?」と大人側がお子さんに頼ることで、お子さんの「期待に応えたい」という頑張るモチベーションを引き出します。
【事例】「話さないと気が済まない子」に効いた!自立への2ステップ
当教室には、「思いつたらすぐに話さないと気が済まない」というお子さんがいました。
初期の支援では、職員が隣でお話を一通り聞いてから学習に促すことで、お子さんに「自分の話を遮らずに聞いてくれる」という安心感を育てました。
その安心感を土台に、次に以下の支援に移していきました。
- 意図的な離席とお願い: 担当職員がわざと他の職員に呼ばれる場面を作り、「ごめんね、ちょっと呼ばれてるから、1問だけ解いていてくれる?」とお願いしました。
- 競争の導入: 別の日には、「先生が戻って来るのと〇〇さんが2問解くの、どちらが早いか試してみよう!」と競争の要素を提示しました。お子さんは誇らしげに「もう終わってるよー」と報告してくれました。
この支援を通じて、お子さんは「誰にも話しかけずに課題を終える」という集中した状態を繰り返し体験し、自己コントロール能力を養うことができました。
比べて実感!実体験を言葉で繋ぐ「集中」の振り返り術
「短時間離席」を続けていく中で、職員はお子さんに「〇〇さん、『集中』する時間が長くなったね」と成長の振り返りを行いました。
お子さんはこの時、『集中して解く』という行為がどんな状態であるかを初めて実体験として理解しました。
その結果、職員が「1分間集中するよ。」と声をかけると、「了解!」と自ら意欲的に問題に取り組めるようになりました。
この事例は、①安心できる時間設定と②大人の頼みに加えて、③成長の振り返りという3つのポイントが組み合わさることで、お子さんの「一人でできる」力を大きく伸ばし、自己コントロールの感覚を明確にすることができた場面でした。
【脳のエンジンをかける】学習効率を最大化する「わずか5分の運動」活用術
集中できない原因は脳の「疲れ」や「眠気」? 集中力と脳の活性化の関係
集中が苦手なお子さんの場合、「疲れ」や「眠気」によって脳が身体を制御するほど活性化していない可能性があります。
特に放課後等デイサービスを利用する時間帯は、お子さんにとって学校での疲れや眠気がピークに達する時間であることが少なくありません。
脳の活動レベルが低いと、衝動的な行動を抑えるのが難しくなり、結果として落ち着きなくソワソワしたり、すぐに立ち歩いてしまったりする行動につながります。
即効性あり!学習前に試したい「血の巡りを良くする」簡単運動2選
脳を活性化させ、集中しやすい状態を作るには、学習の前に軽く運動をして脳に酸素を送るのが効果的です。
特に、血の巡りを良くし、全身の血行を促す「足を大きく動かす運動」がおすすめです。
- スクワット: 膝を曲げる動作は、全身の大きな筋肉を使い脳に酸素をたくさん送るため効率よく脳を活性化します。
- ジャンプ: 軽快なジャンプを数回繰り返す。
わずか5分程度の運動でも、脳のエンジンをかけ、学習への切り替えをスムーズに行うことができます。
【事例】立ち歩きが減った!不安定さが集中を生む「バランスディスク」の秘密

当教室には、「すぐに立ち歩いてしまう」という衝動的な行動が見られるお子さんがいました。
教室では、この立ち歩きの原因を上記の「脳の不活性」によるものと見立て、バランスディスク(上記画像)というツールを導入しました。
支援の秘密:あえて不安定にする
通常、バランスディスクには適量の空気を入れますが、このお子さんに対しては空気を少なめに入れました。
ディスクがブニブニとした不安定な状態になるように調整したのです。
お子さんはこの不安定なバランスディスクに座って学習を行いました。その結果、どうなったでしょうか?
常に不安定な状態でバランスを取ろうとすることで、脳は姿勢を保持しようと活発に働き始めます。
この「姿勢を保持する」ための活動が脳を活性化させ、お子さんは衝動的な動きを制御し、目の前の学習に集中できるようになったのです。
この事例は、単に座らせるのではなく、適切な「動き」を学習に取り入れることが、集中力向上につながることを示しています。
【根本解決!】集中力・自己制御の土台は「体力」だった!
一時的な集中力アップで終わらせない!将来を見据えた最も重要な土台とは?
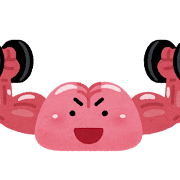
ここまで、私たちは「刺激」「集中」「脳の活性化」という3つのテクニックをご紹介しました。
しかし、最後に最も重要な根本的な支援をお伝えします。そのキーワードは、「体力」です。
学習活動を妨げる「疲れ」や「眠気」は、脳の活動レベルを低下させます。
脳が活発に働いていない状態では、衝動を抑えるのが難しくなり、自分の行動を制御する力も弱くなります。
この自己制御に必要な「脳が活動的でいられる時間」を長くするには、体力が必要です。
つまり、お子さんの集中力や自己制御の力は、体力の増減と深く関係しているのです。
一時的なテクニックではなく、長期的な視点でお子さんの将来を考えると、「体力をつけること」が最も重要な土台になってきます。
体力が変われば集中力が変わる!日常で始める簡単トレーニング
特別な場所や道具は必要ありません。
お子さんの将来を見据え、ぜひ日常で以下の簡単トレーニングを継続してみてください。
- いつもより長く歩く:意識して少し遠回りをするなど、有酸素運動の機会を増やします。
- 筋肉トレーニングをしてみる:壁押しや軽いスクワットなど、体幹に負荷をかける遊びを取り入れます。
- 生活習慣を見直してみる:睡眠や食事の質を整え、疲れをためない生活習慣を確立します。
これらの継続によって体力がつけば、脳が長く活動的でいられるようになり、お子さんの変化を感じられるはずです。
【事例】「もうやりたくない」と寝転んでいた子が安定した学習に向かえた理由
当教室には、「勉強がしたくなくてすぐに床に寝転んでしまう」お子さんがいました。
入会当初からお母様は「体幹がない」と話しており、学習中もお子さんの体勢は徐々に崩れ、「もうやりたくなーい」と訴えてしまう状態でした。
しかし、そのお子さんの体が著しく大きくなった時期と、床に寝転ぶ行動が減った時期が一致したのです。
体格ががっしりとしてくると、ソワソワした様子がなくなり、体勢が崩れることが激減しました。
体が安定したことで、それまで嫌いだった解答の直しにも冷静に向き合えるだけの余裕が生まれました。
これは、体力がついたことで、お子さん自身が自分の行動を長く制御できるようになった明確な例です。
集中力のテクニックと同時に、体力の土台を育むことを強くお勧めします。
【自立のための学習支援】当教室が「ソワソワ」をなくさない理由
【逆転の発想】「ソワソワ」をなくすことを目的にしないワケ
私たちは、お子さんのソワソワやキョロキョロといった行動に対して、「なくすこと」を目的としていません。
その行動の根本的な原因を探り、「刺激に対する欲求を満たす方法を考える」という視点を大切にしています。
背中トントンや短時間離席といった手法は、お子さんの「困りごと」ではなく、「満たされないニーズ」に寄り添い、行動をコントロールする術を教えるためのものです。この支援の根幹には、当社の企業理念である『自立のための学習支援』があります。
自立した社会人へ!「自分の苦手」を言語化できる強さ
将来、社会に出て行く際、お子さんが自分の特性を理解していることは大きな強みになります。
自分がどんなことや場面が苦手か、どうすれば社会との壁を解消できるかを言葉にできる力こそが、生きる上での最大の武器です。
実際に、障害者雇用を行う企業が最も求める人材は、PCスキルや事務スキルの高さよりも、
「毎日健康に休まず通える人」、そして「自分に必要な配慮を言語化できる人」
だと言われています。
オレンジスクールつくば教室では、お子さんの苦手や生きづらさの解消をご家庭と一緒に考えながら進めていきます。
************
こだわり、学習遅滞、不登校、多動、注意散漫、音に敏感など、お子様の発達・成長・学力でご不安なことがありましたら、ご相談ください。
・準備や時間管理が苦手
・空気を読むことが難しい
・こだわりがあり学習にも偏りが多い
・意外なことで突然癇癪を起す
・不登校で勉強が遅れている
・算数や国語の問題内容をイメージするのが苦手
放課後等デイサービス オレンジスクールつくば教室
【TEL】029-886-6653
【MAIL】tsukuba@orangeschool.jp
【お問い合わせ】 放課後等デイサービス オレンジスクール つくば教室
************
つくば教室の近隣には、竹園西小学校・竹園東小学校・竹園東中学校・吾妻小学校・吾妻中学校・手代木南小学校・手代木中学校・並木小学校・並木中学校があります。
※自治体の助成により無料もしくは低額にて療育・学習指導が受けられます。
まずは、市役所/相談支援事業所/当事業所にご相談ください。
※放課後等デイサービスは、「放デイ」「放課後デイ」「放課後デイサービス」と略して呼ばれてもいます。